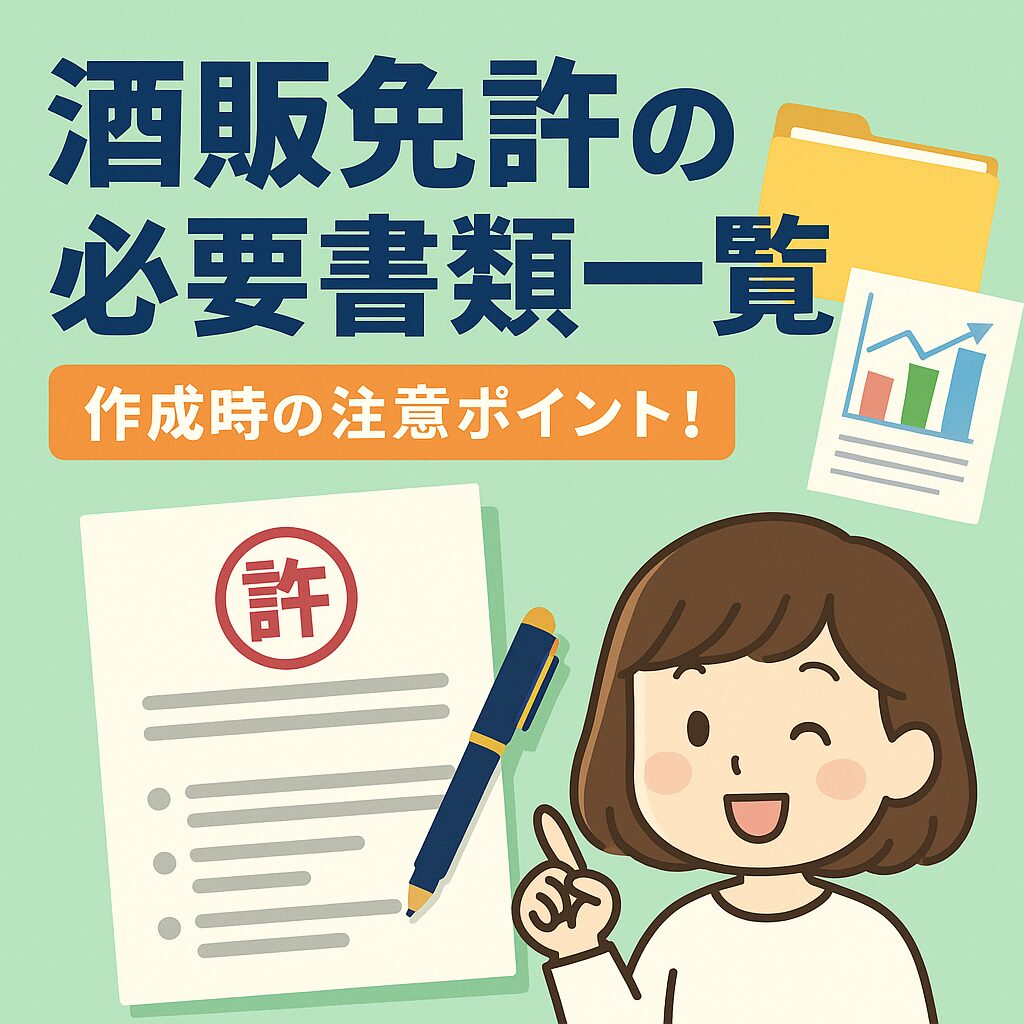はじめに
酒類販売業を始めるにあたり、最初の大きな関門となるのが「酒販免許」の取得です。その中でも、多くの申請者が頭を悩ませるのが「必要書類」の準備です。この記事では、酒販免許取得に必要な書類を網羅的に紹介し、それぞれの書類についての注意点や作成のコツを解説します。個人事業主や副業としての酒販を検討している方にも役立つ内容となっています。
 たまちゃん
たまちゃん書類不備があると再提出になってしまうから、準備は慎重にね!
酒販免許申請に必要な主な書類一覧
以下は、一般的な「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」において共通して提出が求められる主な書類です。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 酒類販売業免許申請書+次葉1~6 | 申請者の基本情報、申請する免許の種類などを記入する主文書 |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 法人の場合、代表者だけでなく役員の分も必要 |
| 販売場の平面図および周辺図 | 実際に販売を行う場所の詳細なレイアウトと周辺環境を示す図面 |
| 建物の使用権限を証する書類(賃貸の場合) | 所有権証明書または賃貸借契約書など |
| 履歴書・経歴書(申請者) | 酒販経験や職歴を記載。特に役員が複数いる場合は全員分必要 |
| 営業の概要書(パンフレット等) | 取り扱う予定の酒類の種類、販売方法、営業日など |
| 資金調達方法および運転資金の内容 | 自己資金の明細や銀行残高証明書など |
| 直近3事業年度の財務諸表 | 経営の健全性を判断 |
| 納税証明書 | 国税および地方税の未納がないことを証明する書類 |
| 定款および登記簿謄本(法人の場合) | 会社の存在と目的の正当性を証明 |
| その他の書類 | 事業計画書や使用承諾書などが求められることも |



酒販免許の種類によって微妙に必要書類が異なることもあるから、事前に税務署に確認するのがベストだよ!
書類作成時の注意点
1. 書類の不備は再提出の対象
酒販免許は、他の営業許可と比べてもかなり審査が厳格です。不備があると、すぐに差し戻しとなってしまいます。記入漏れ、添付漏れ、日付のミスなど、小さなミスが致命的になることも。
2. 書式は必ず最新版を使用する
税務署のWebサイトに掲載されている様式を使用するか、窓口で直接もらうようにしましょう。古い書式を使うと受け付けてもらえない可能性も。
3. 平面図・周辺図は正確に
販売場の図面は、税務署職員が酒類販売場所や保管場所の確認を行う際の重要な判断材料です。見取り図程度ではなく、寸法付きのしっかりした図面を作成しましょう。
4. 納税証明書は発行日数に注意
これらの証明書には「申請日から3か月以内の発行」という有効期限があるため、タイミングを見計らって準備しましょう。あまりに古い証明書は受理されません。
よくあるミス事例
- 平面図に出入口やカウンター位置が記載されていない
- 使用権限の証明書が「写し」になっている(原本必須)
- 資金証明が足りない(自己資金と借入予定資金が合計されていない)
- 申請者と名義人が異なる建物を使用予定



ちょっとしたケアレスミスが後々の手間につながるから、ダブルチェックを忘れずに!
書類提出後の流れ
書類を提出したら、税務署での審査という流れになります。形式審査の段階で不備があれば差し戻し、許可調査では販売場の状態や営業実態の確認が行われます。
許可までの期間は概ね2か月程度ですが、不備があれば延びるため、提出書類の精度は非常に重要です。
書類作成をプロに依頼するメリット
酒販免許申請の書類は、量が多く、内容も複雑です。特に法人の場合は提出書類が倍増します。行政書士などの専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 書類の抜け漏れを防げる
- 不備による差し戻しを回避できる
- 地域の事情に合わせた書類作成が可能
- 忙しい中でもスムーズに申請を進められる



自分でやるのもいいけど、不安なら酒販免許のプロである行政書士に頼むのが早道だよ~!
まとめ
酒販免許の取得において、必要書類の準備は最も大変かつ重要なステップです。この記事で紹介した書類一覧と作成時の注意点を参考に、抜かりなく準備を進めましょう。どうしても不安な方は、酒販免許に詳しい行政書士などの専門家への相談も検討してみてください。
申請は慎重に、準備は確実に!酒販免許の第一歩をしっかり踏み出しましょう!