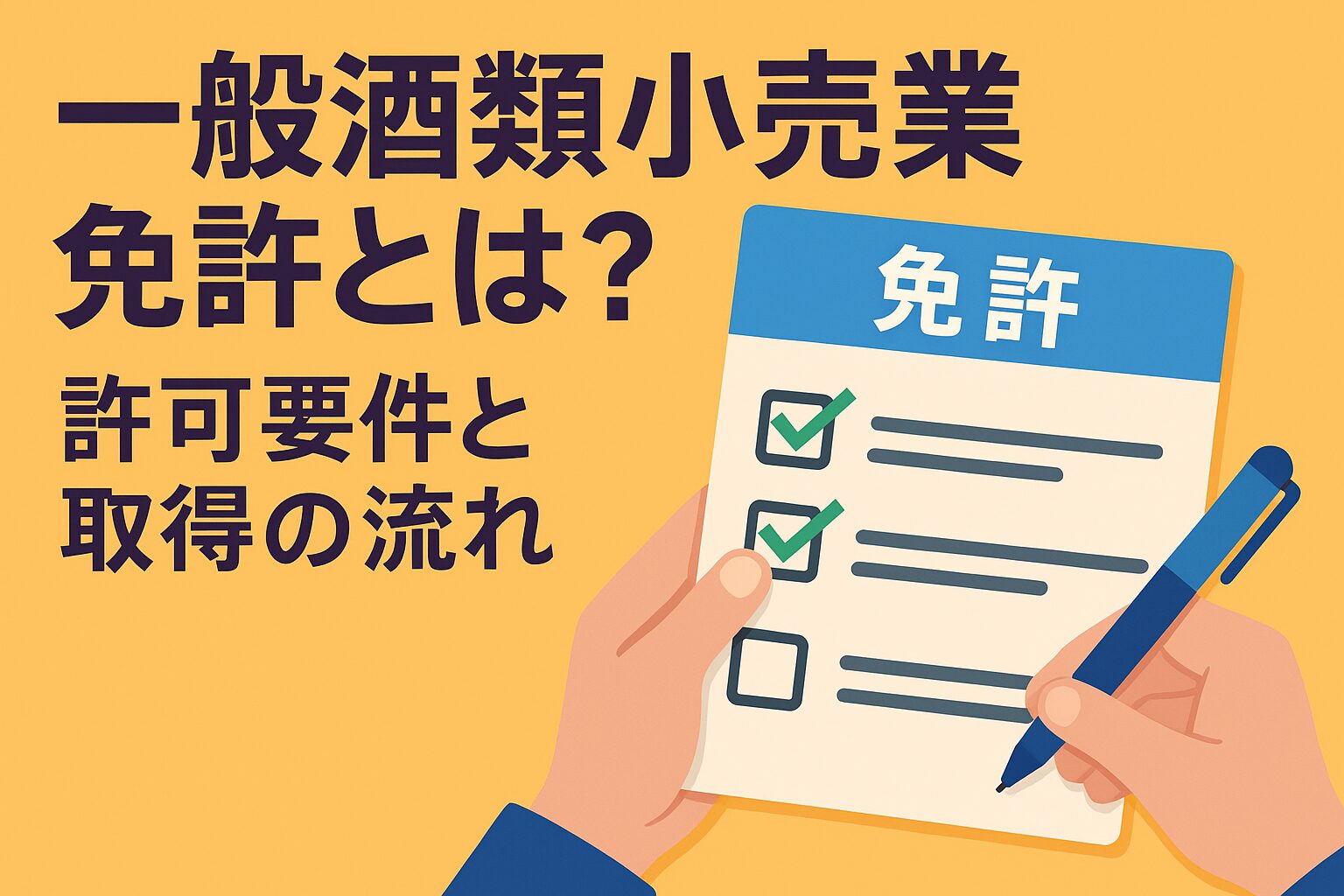第1章:一般酒類小売業免許とは?
「一般酒類小売業免許」とは、店舗などで一般消費者に対してお酒(酒類)を販売するために必要な免許です。これは、対面販売が基本となる免許で、酒販店やスーパー、コンビニなどが対象となります。
この免許の大きな特徴は、誰にでも販売できるという点です。特定の法人や飲食店相手ではなく、不特定多数の消費者に対して、店頭で酒類を販売することが可能となります。
 たまちゃん
たまちゃん“通販じゃなくて店頭で売る”という場合は、まずこの免許が必要なんだよ〜
第2章:誰が対象?取得できる人・できない人
一般酒類小売業免許は、法人でも個人でも申請が可能です。ただし、酒税法第10条により「欠格事由」に該当する者は免許を取得できません。
欠格事由の主な例:
- 過去に酒税法違反などで処分を受けたことがある
- 暴力団等との関係がある
- 経理的基礎が著しく不安定と判断される



“金銭的な信用がない”とか、“素行に問題あり”って思われると、免許は下りないから注意してね〜
第3章:販売場所の重要性
酒販免許は、「販売場所ごと」に取得が必要です。つまり、自宅と別に酒類を販売したい場所がある場合、その販売場の住所に対して免許を申請することになります。
注意すべき点:
- 本店所在地ではなく「販売場の所在地」が重要
- 使用権限のあることを証明する必要あり(賃貸契約書など)
- 建物の用途や構造が適切かも審査される
第4章:許可要件の具体的内容
1. 人的要件
- 販売管理者を選任すること(研修受講が必要)
- 社会的信用のある人物であること
2. 場所的要件
- 設備や建物が販売に適していること
- 保健所・消防などの他法令に違反していないこと
3. 経営基礎要件
- 安定した事業計画があること
- 原則として、半年〜1年分の運転資金があること



お酒は“嗜好品”だけど、売る側はちゃんとした社会的責任があるってことだね!
第5章:申請から許可までの流れ
- 相談・準備
- まずは酒類指導官に相談(酒類指導官設置税務署にて)
- 書類一式の確認
- 申請書類提出
- 管轄税務署に提出(販売場所の所在地を管轄)
- 審査期間(標準処理期間)
- 約2か月程度
- 免許交付
- 書類に不備がなければ、免許が下りる
第6章:提出先と酒類指導官について
申請は「販売場所の所在地を管轄する税務署」に行います。ただし、酒販免許に関する詳しい相談や事前チェックは、税務署の中でも「酒類指導官」がいる税務署でしか対応できません。
酒類指導官設置設置事務所:神奈川県の例
第7章:取得に必要な書類
主な書類は以下のとおりです:
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の位置図、平面図
- 賃貸契約書
- 登記簿謄本(土地、建物、法人)
- 財務状況がわかる書類(決算書・残高証明など)
- 定款の写し(法人)
- 酒類販売管理者研修の修了証
※上記以外にも提出すべき書類はたくさんあります。また、申請する種類によっても用意すべき書類は異なります。



“書類集め”が最大の山場かもしれないね!抜けモレがないようにしよう!
第8章:まとめ・よくある質問
Q1. 飲食店で提供するだけなら、この免許はいらないの?



はい。飲食店でお酒を提供する(グラスに注ぐ)だけなら、一般酒類小売業免許ではなく、飲食店営業許可でOKです。
Q2. 通販やネット販売をしたい場合は?



一般酒類小売業免許とは別に「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
Q3. どのくらいで取得できる?



通常は2ヶ月程度です。ただし、書類の不備があるとそれ以上かかる可能性も。
Q4. 酒販免許は引き継げる?



法人の場合、代表者変更や譲渡に応じて変更届が必要です。個人事業では引き継ぎ不可です。
最後に
一般酒類小売業免許は、個人で副業として酒販を始めたい人から、小売業としてしっかりビジネスを展開したい法人まで、幅広いニーズに対応した免許です。取得までには書類の整備や審査対応など一定の準備が必要ですが、その分しっかりとした事業計画の構築が可能になります。



自力でやろうとすると時間もエネルギーもいるので、困ったときは専門家に相談してみてね!