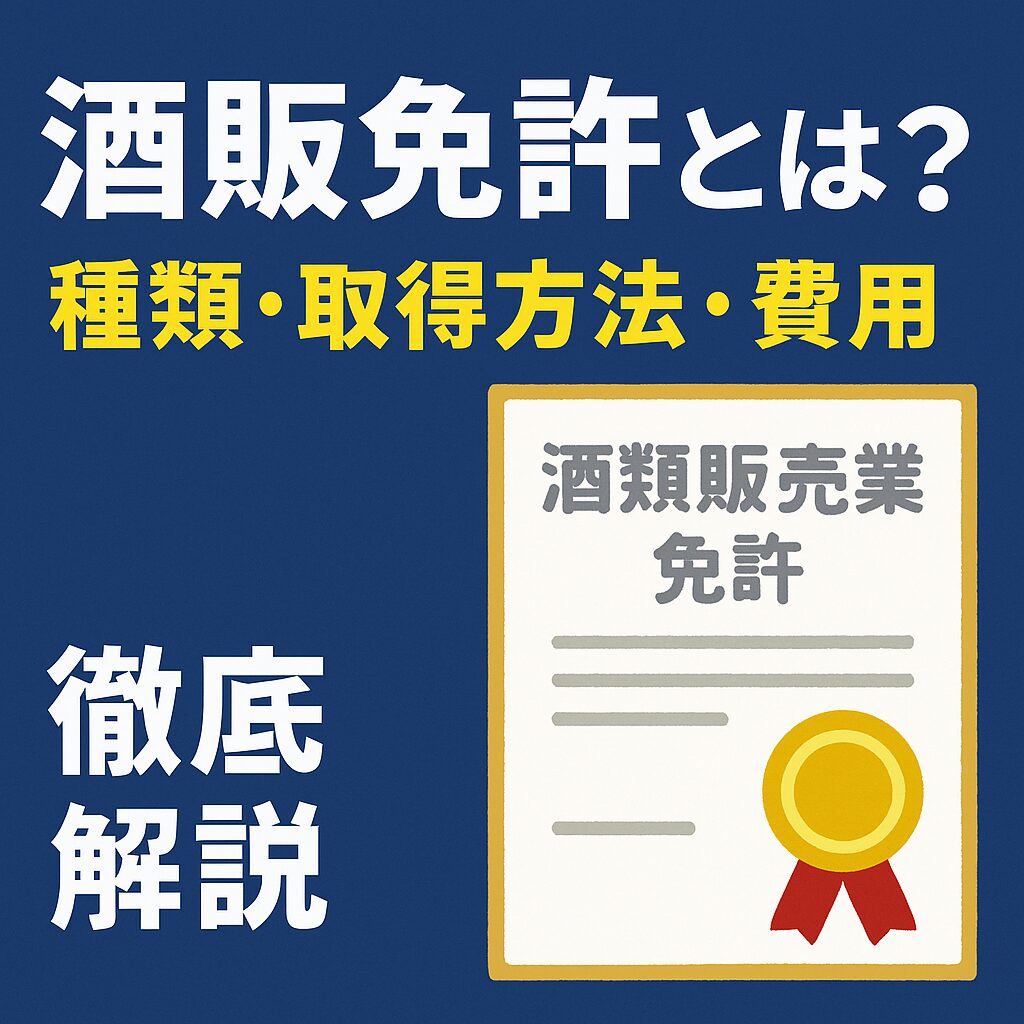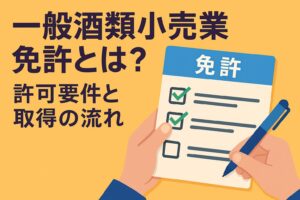はじめに:酒販免許の基礎知識
副業としてお酒の販売を考えている方や、個人事業主として酒類を取り扱いたい方にとって避けて通れないのが「酒販免許」です。本記事では、酒販免許の種類や申請要件、実際に取得するまでの流れ、必要な費用などを網羅的に解説します。
 たまちゃん
たまちゃんふむふむ。最近は個人でワインを販売したいとか、キャンプ場で地ビールを出したいとか、いろんな人が酒販免許に興味を持ってるよ。そんな人向けのガイドだよ!
1. 酒販免許とは?
酒販免許とは、酒類の販売を行うために必要な国税庁(税務署)発行の許可です。日本では、酒類の製造・販売は厳しく規制されており、販売を行うには必ずこの免許が必要となります。無免許で酒を販売すると、酒税法違反として重い罰則が科されます。
法的根拠:
- 酒税法第9条:「酒類を販売しようとする者は、所轄税務署長の許可を受けなければならない。」
- 国税庁通達:販売形態や販売場所によって、異なる免許が必要であることが明示されています。
酒類販売は、個人でも法人でも許可が必要で、販売場所や方法、取引相手によって求められる免許の種類も異なります。
2. 酒販免許が必要なケースとは?
酒販免許は、次のような場合に必要です:
- インターネットで酒類を販売(ネットショップ)
- 店舗で酒を販売(酒屋、土産物店)
- キャンプ場などの現地販売
- 飲食店でのテイクアウト販売(※別途扱いあり)
- 個人でヤフオク・メルカリ等で酒類を継続的に販売
不要なケース:
- 自宅で自分で飲むために購入
- 贈与や一時的な譲渡(ただし利益が発生する場合はNG)



『ヤフオクでちょっと売るだけ』でも継続的なら免許が必要!気をつけてね〜
3. 酒販免許の大まかな種類一覧
| 免許の種類 | 販売対象 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 一般消費者 | 酒屋、土産店、飲食店での小売 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 一般消費者 | ネット通販、ECサイトでの販売 |
| 酒類卸売業免許 | 酒販店や飲食店 | 業務用・飲食業者向け販売 |



誰に販売するのかによって、取得すべき免許の種類が変わります。つまり、業者に販売する場合は卸売業免許、一般消費者に販売する場合は小売業免許となります。
4. 酒販免許の取得要件
主な要件:
- 人的要件:申請者が成年であり、禁固刑などの前科がないこと。過去に免許取消の経歴がないこと。
- 場所的要件:販売場(店舗や事務所)が確定していること。居住地や自宅では不可の場合もある。
- 経営基礎要件:安定した経営が見込まれること。自己資金が十分であること。
- 需要調整要件:酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。



酒販免許は“誰でも簡単に取れる”わけじゃないよ。けっこうシビアに審査されるよ〜ん。


5. 必要書類一覧
申請に必要な書類は以下の通りです(一例。実際にはもっとたくさんあります)
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の賃貸借契約書または登記簿謄本
- 納税証明書
- 経歴書
- 誓約書(遵法性の確認)
- 定款の写し(法人)
※申請する種類によっては追加書類を求められる場合があります。例えば通信販売の場合は年齢確認のためのフォーム画面や商品購入画面のサンプル等が求められます。
6. 酒販免許の取得までの流れ
- 事前相談(推奨):販売場所在地を管轄する税務署の「酒類指導官」へ相談
- 必要書類の収集
- 申請書類の提出(窓口または郵送)
- 審査(通常2か月程度)
- 許可通知の受領
- 販売開始
7. 費用・手数料について
酒販免許自体に登録免許税(3万円)が必要です。また、申請書類の準備にあたり、行政書士など専門家へ依頼する場合の書類作成報酬は約10万〜15万円程度が相場です。



税務署に払うのは3万円だけど、プロに頼むときはそれなりに費用がかかる。。でも時間と手間を考えると価値アリかもね〜
8. よくある落とし穴・注意点
- 自宅を販売場にする場合は注意(住居専用地域では不可)
- 販売場が未定では申請不可
- 副業でも継続的販売なら免許必須
- 事前相談なしで提出すると受理されないこともある
9. まとめ:副業でもしっかり準備を!
酒販免許は、正しく申請すれば個人や副業でも取得可能です。しかし、書類の多さや要件の厳しさなど、簡単なものではありません。この記事を参考に、まずはしっかりと全体像を把握し、自身のケースに当てはめて準備を進めていきましょう。



まずは販売場を確定させて、税務署に相談してみるところから始めよう〜!わからないときは行政書士に相談するのもアリ!