はじめに
酒類販売業を営むにあたり、法律で定められた研修の受講が求められるケースがあります。それが「酒類販売管理研修」です。本記事では、酒類販売管理研修とは何か、誰がいつ受講すべきなのか、費用や受講場所、受講の流れについて詳しく解説します。
 たまちゃん
たまちゃん研修って聞くと堅苦しく感じるかもしれないけど、実はすごく大事なポイントなんだよ~
1. 酒類販売管理研修とは
酒類販売管理研修とは、酒類販売における法令遵守や適正な販売管理を目的として、国税庁が実施を求める研修制度です。販売者に対し、酒類の未成年者飲酒防止、転売対策などに関する知識を習得させることを目的としています。
研修の根拠法令は以下の通りです。
- 酒税法第86条の12
- 酒類の販売の管理の状況の届出等に関する命令(平成18年財務省令第6号)
この研修は、酒類販売業の適正な運営と社会的責任の遂行を担保する制度です。



経営基礎要件の中の「経歴及び経営能力等」の項目に、酒類販売の業務に従事したかどうかが問われていますが、それは絶対条件ではなく、酒類販売未経験であったとしても、「酒類販売管理研修」を受講することにより、要件を満たすものとみなされます。
2. 受講が義務付けられるケース
以下の場合、酒類販売管理研修の受講が義務づけられています。
1:酒販免許を新たに取得する場合
新規で一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などを取得する際、営業開始から3か月以内に研修を受講する必要があります。
2:既存の酒販免許保有者のうち、前回の受講から3年が経過した場合
3年に1回の頻度で、定期的に受講が必要です。
3:酒類販売管理者を新たに選任する場合
法人・個人問わず、酒類販売管理者を変更する場合、新たに選任された者が3か月以内に研修を受講しなければなりません。



3年おきの更新って意外と忘れがちだから、カレンダーとかにメモしておこうね♪



「更新期限が近づきました」という旨のはがきが、前回管理者研修を受講した主催者から届くこともあります。
3. 誰が受講すべきか
原則として、酒類販売管理者が受講すべきですが、販売場において実質的な管理を行う人が複数いる場合は、代表的な責任者が受講すれば問題ありません。法人の場合は役員の方のどなたかが受講することが望ましいとされています。
なお、研修を受けた旨を販売場に掲示することが義務付けられており、未掲示は指導の対象になります。



新規で酒販免許を取得する場合、早い段階で(申請書を提出する前に)開催場所と日程を確認して受講しましょう。国税庁のHPに研修情報の記載があります。申請書に研修の受講日と研修団体の記入欄がありますので、そちらにももれなく記入します。
4. 酒類販売管理研修の内容
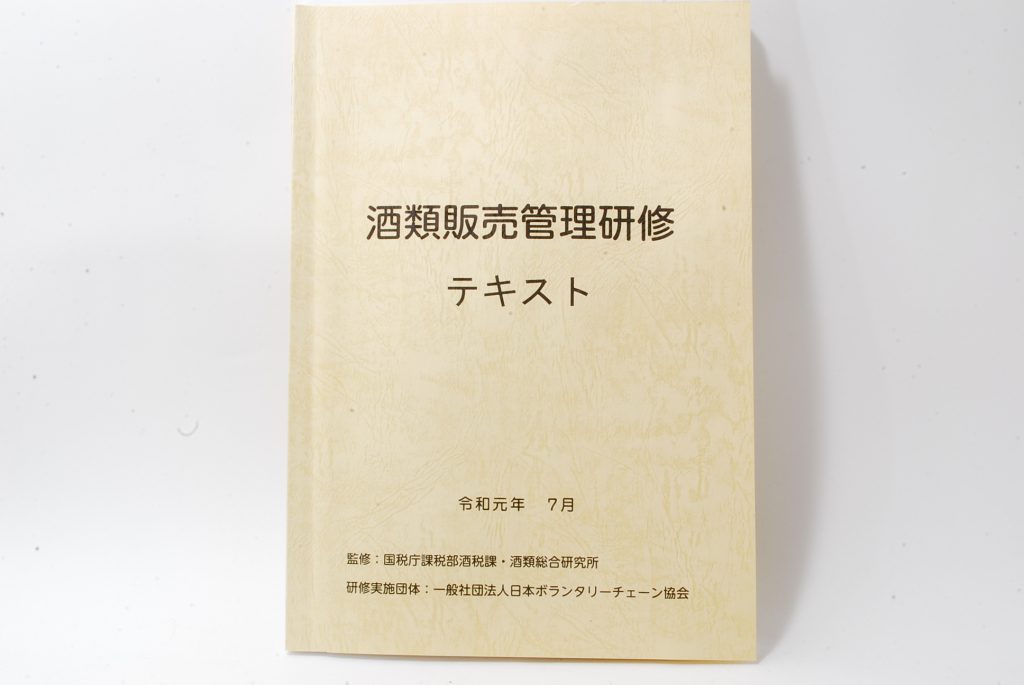
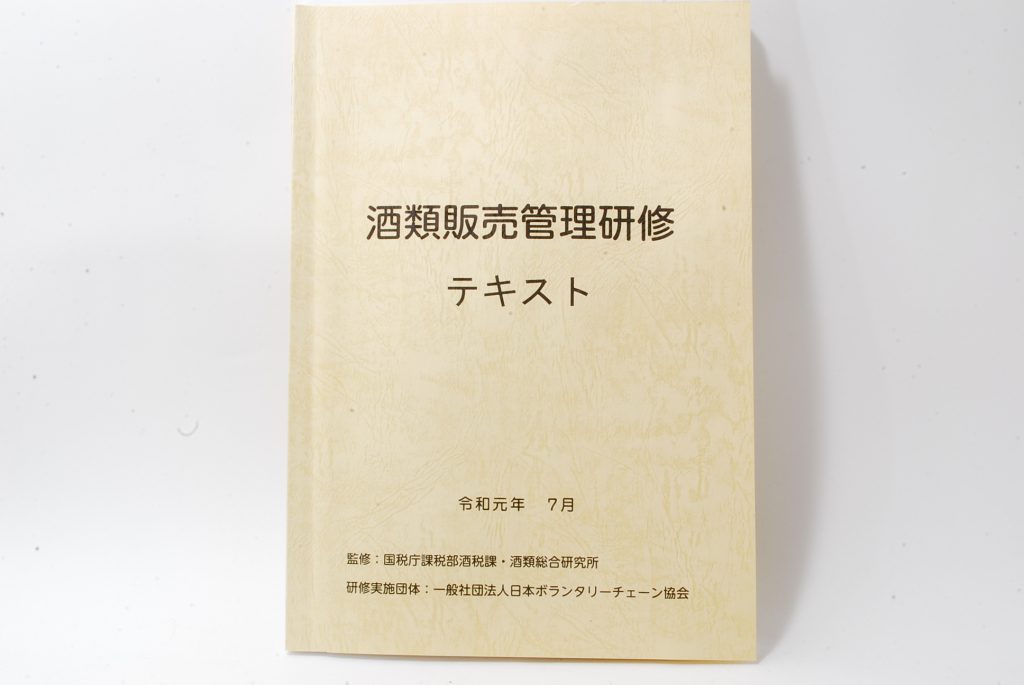
研修は通常、以下のようなカリキュラムで構成されています。
- 酒税法および酒類販売に関する法令の概要
- 未成年者飲酒防止に関する注意事項
- 酒類の適正な販売方法
- 酒類の転売防止に関する管理体制



所要時間はおおむね3時間程度。筆記試験などはなく、講義形式で行われます。酒販業務未経験の方にとっては非常に勉強になる、濃密な研修だと思います。酒販業務経験がある方にとっても初心に帰る意味においても有意義な研修だと言えるでしょう。
5. 受講方法と開催団体
開催団体
酒類販売管理研修は、以下のような団体が定期的に開催しています。
- 日本ボランタリーチェーン協会(JBCA)
- 日本フランチャイズチェーン協会(JFA)
- 新日本スーパーマーケット協会
- 日本チェーンストア協会
- 各都道府県の小売酒販組合 など
受講方法
- 開催日程を各団体の公式サイトで確認
- 電話やWebフォームで申込
- 開催当日、所定の会場にて受講
- 修了証の発行(掲示用)



自分の都合の良い日程に合わせて受講しましょう。会場もまたバラバラなので、よく確認して下さい。なお、オンライン受講は現在一部団体で対応していますが、対面形式が基本です。
6. 研修の受講費用
受講費用は開催団体によって異なりますが、一般的には3,000円〜4,000円程度です。一部の業界団体では、自団体の会員に対して割引価格で提供しているケースもあります。



費用は経費計上できるから、ちゃんと領収書もらっておこうね!
7. 修了証と掲示義務
研修受講後には「酒類販売管理研修修了証」が発行されます。これは販売場に見やすく掲示する義務があります。万が一、未掲示の場合や期限切れの場合、税務署からの指導対象となることがあります。



通信販売の場合であっても、販売場に掲示する必要があります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1:研修を受けなかった場合の罰則はありますか?



罰則規定はありませんが、税務署からの行政指導の対象となり、最悪の場合、営業停止や免許取消に至ることもあります。
Q2:販売員全員が受講する必要がありますか?



いいえ、販売場ごとに1名以上の管理者が受講していればOKです。ただし法人の場合、管理者とは別に役員の方が受講している必要があります。
Q3:受講証を紛失したらどうすれば?



発行団体に再発行の手続きを行ってください(手数料がかかる場合あり)。
おわりに
酒類販売管理研修は、酒販免許を持つ全ての販売場において、適正な運営を行うための基本です。忘れがちな「3年に1回」の定期受講を含め、確実に対応しておきましょう。
今後、研修のオンライン化や制度改正が行われる可能性もあるため、最新情報を常にチェックしておくことも重要です。



研修は“面倒”じゃなくて“安心”への第一歩!しっかり受講して、お酒の販売を楽しく安全に続けようね!



酒販業務未経験の方にとっては非常に勉強になる、新鮮かつ濃密な研修だと思います。酒販業務経験がある方にとっても初心に帰る意味においても有意義な研修だと言えるでしょう。












