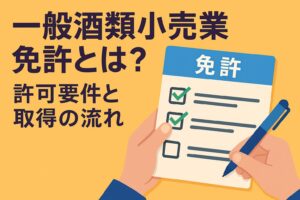はじめに:飲食店営業許可と酒販免許の違いにご注意を
飲食店を開業しようとする際、必ずと言っていいほど登場するのが「飲食店営業許可」と「酒販免許」という2つの許認可です。一見すると似ているこの2つの制度ですが、実はそれぞれ異なる目的と管理機関があり、混同すると思わぬトラブルや違法行為に繋がる可能性があります。
本記事では、飲食店営業許可と酒販免許の違いを中心に、注意すべき点や両者を組み合わせた運用のポイントまで徹底解説します。
 たまちゃん
たまちゃん飲食店でお酒出せるからって、お酒のボトルもついでに販売できるって思ってたら大間違いだよ~!
飲食店営業許可とは? – 保健所が所管する飲食の営業資格
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき「飲食物を調理・提供する事業」を行うために必要な許可で、所管は各自治体の保健所です。
主な要件
- 営業施設の構造・設備が基準を満たしていること
- 食品衛生責任者を設置していること
- 定められた手続きを踏んで申請し、保健所の検査に合格すること
この許可があれば、料理や飲み物(アルコール含む)を店舗内で提供することができます。ただし注意すべきは、「店内での提供」に限られるという点です。
酒販免許とは? – 国税庁(税務署)が所管する酒類販売の許可
酒販免許(正式には「酒類販売業免許」)は、酒税法に基づき「酒類を販売する事業」を行うために必要な許可で、申請先は販売場所を管轄する税務署です。
主な種類
- 一般酒類小売業免許(店頭販売)
- 通信販売酒類小売業免許(ネット販売)
- 酒類卸売業免許(事業者向け)など
この許可があると、酒類を一般消費者に販売することができます。ただし、飲食店営業許可とは異なり、販売後の「飲用場所」には関与しません。



酒販免許は“売る”ための免許。グラスに注いで提供するのとは別なんだね!
両者の違いを比較:目的・管轄・書類・審査の違い
| 項目 | 飲食店営業許可 | 酒販免許 |
|---|---|---|
| 管轄機関 | 保健所(自治体) | 税務署(国税庁) |
| 根拠法令 | 食品衛生法 | 酒税法 |
| 対象業務 | 調理・提供 | 販売 |
| 申請書類 | 設備図面、衛生責任者証など | 経営基礎要件、人的要件、場所的要件など |
| 申請難易度 | 比較的容易 | 高め(審査厳格) |



飲食店営業許可は自力でできても、酒販免許を自力でやるのは難しい!
飲食店営業許可で“お酒の販売”はできるのか?
結論から言えば、店内での飲用に限り提供可能です。つまり、お客様が店内で食事と一緒にビールやワインを飲む場合、飲食店営業許可があれば対応可能です。
ただし、お客様が「瓶ビールを家に持ち帰りたい」と言った場合には、酒販免許が必要になります。そのまま販売してはいけません。



例えば売店でビールを販売する場合は、その売店内でグラスに注いで提供する分には飲食店営業許可だけで足ります。しかし、通常は売店ではグラスに注いで提供するよりもビールの缶をそのまま販売することのほうが多いと思います。そうなると、売店でビールを販売するためには酒販免許が必要となります。
その逆、酒販免許があれば店内で飲ませてもOK?
答えは「NO」です。酒販免許はあくまで「販売」目的のものであり、調理・提供行為を伴う「飲食サービス」は含まれていません。したがって、酒販免許だけで飲食店営業をすることはできません。飲食店営業許可申請をする必要があります。



たとえば酒屋さんが店内でお酒を飲ませたらダメってこと!
注意!飲食店で「持ち帰り用の酒」販売するには?
飲食店営業許可しか持っていない状態で、お酒を「テイクアウト用に販売」することは違法行為となります。例えば、ボトルワインを棚に並べて「持ち帰りOK」と販売する場合は、酒販免許が必要です。酒販免許を取得していないと、税務署からの指導や罰則の対象となる可能性があります。
飲食店が酒類を提供する場合の「表示・税務・管理」義務
飲食店でアルコールを提供する場合には、次のような義務・注意点があります:
- 酒類の仕入れ先は正規ルートから行う(納品書の管理)
- メニュー表記でアルコール度数や原産国などに誤りがないこと
- 酒税法違反とならないよう、管理を徹底する(酒類販売管理研修を受けた従業員を置くことは義務ではないが推奨)
酒販免許が必要なケースと不要なケースの判断基準
| シチュエーション | 酒販免許の要否 |
|---|---|
| 店内でビールを提供する | 不要(飲食店営業許可) |
| ワインを持ち帰り販売する | 必要(酒販免許) |
| ECサイトで地酒を販売する | 必要(通信販売の酒販免許) |
| ウェディング会場で乾杯用シャンパンを出す | 不要(飲食店営業許可) |



シチュエーションによって酒販免許が必要な場合とそうでない場合があるので、しっかり確認しよう!
飲食店経営者がよくやりがちなNG事例と対応策



飲食店営業許可だけでは販売不可。酒販免許が必要です。



通信販売酒類小売業免許が必要です。



名義貸し・借りは厳禁。即取消対象となります。
飲食店+酒販免許を組み合わせた副業・事業モデル
近年では、飲食店+酒販免許を組み合わせて次のような展開をする事業者も増えています。
- 店内でワインを提供しつつ、棚で販売も行う(ボトル販売)
- クラフトビールバーで、店内提供+ネット通販展開
- お土産用に地酒や限定酒を販売



副業的に始める場合でも、法令遵守は必須です。安心・確実にビジネスをするうえでも、酒販免許が必要な場合は必ず取得したうえでビジネスを展開していきましょう。
まとめ:飲食店と酒販免許、正しく理解して賢く運用しよう
飲食店営業許可と酒販免許は似ているようで、まったく異なる性質の許可です。それぞれの許可がカバーする範囲と、取得すべきタイミングを理解していないと、結果として営業停止や罰則を受けるリスクもあります。
飲食店経営者や開業予定の方は、自分が提供したいサービスにどの許可が必要なのかをしっかりと把握した上で、適切に準備を進めていきましょう。



わからなければ、酒販免許に強い行政書士に聞くのも大事だよ~!