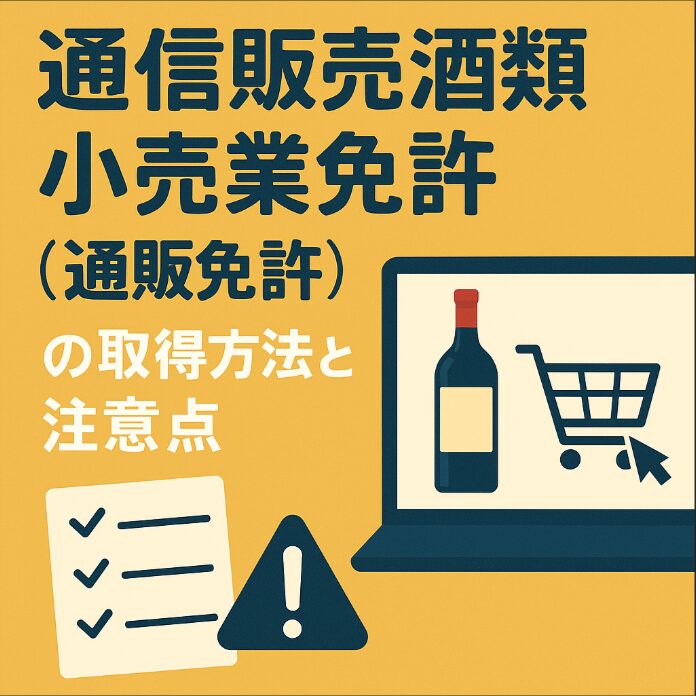はじめに
近年、インターネットを通じて酒類を販売する「通信販売酒類小売業」が注目を集めています。リモートワークや巣ごもり需要の高まりを背景に、自宅でお酒を楽しむ人が増え、酒販業界でもEC化が加速しています。
本記事では、「通信販売酒類小売業免許(通称:通販免許)」を取得したい方向けに、必要な要件や申請手続き、注意点について網羅的に解説します。
 たまちゃん
たまちゃん酒屋さんもオンライン時代へ!通販免許があれば全国へお酒を届けられるんだよ~
第1章:通販免許とは?
通信販売酒類小売業免許の定義
通信販売酒類小売業免許とは、酒税法第9条に基づく免許の一つで、郵便・インターネット・電話などを通じて、酒類を一般消費者に販売することを認める免許です。
この免許により、実店舗を持たずに自社のECサイトやECモール(楽天・Amazonなど)で全国の消費者へ酒類を販売することが可能となります。
第2章:取得できるお酒の種類
通信販売免許では、販売できる酒類に制限があります。以下のどちらかに該当するもののみ販売可能です。
- 輸入酒類
- 国産酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
- 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類



国産のお酒だと、地酒やクラフトビールみたいに地域性のあるお酒が対象になるんだね~
第3章:取得要件
1. 経営基盤の安定性
過去に重大な法令違反や納税遅延がないこと、健全な経営体制であることが求められます。
2. 販売場の設定
「通信販売であっても販売場の実在」が必要です。これは、自宅兼オフィスであっても可能ですが、飲食店など他業態との兼業施設では難しいケースもあります。
3. 販売システムの整備
販売方法の詳細(自社サイト/ECモール)、商品管理、決済手段、配送体制、返品対応などの仕組みを明示する必要があります。
4. 酒類販売管理者の設置
講習を修了した販売管理者を1名以上置く必要があります。
第4章:申請に必要な書類の一例
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の図面
- 賃貸借契約書の写し
- 販売方法の詳細
- 会社登記事項証明書(法人の場合)
- 履歴書
- 納税証明書
- 酒類販売管理者研修修了証明書
このほか、販売形態等により税務署から追加で書類を求められる場合がございます。



図面とか契約書も必要だから、事前準備はしっかりしておこうね〜!
第5章:申請の流れ
- 管轄税務署(販売場の所在地)に事前相談
- 書類の準備・提出
- 税務署による審査(通常2か月程度)
- 審査完了後、免許証交付
- 酒類販売開始(サイト公開・発送体制整備)
第6章:通販免許のメリット
- (一定条件下において)全国へ販売可能
- 実店舗不要(固定費削減)
- 時間・場所に縛られず営業可
- 地域特産品のブランディングに有利
第7章:注意点とよくあるミス
1. 通常の酒販免許と誤認する
実店舗での販売が主な「一般酒類小売業免許」とは別物です。販売形態によって使い分けましょう。
2. 対象外の商品を販売してしまう
例えば大手国産メーカーが製造したお酒などは対象外になるため要注意です。
3. 酒類販売管理者の不在
管理者がいない場合、違法販売として摘発される可能性があります。
第8章:開業後の注意点
- 年次報告書の提出
- 酒類販売管理者の定期的な研修(3年以内に再受講)
- 消費者クレーム対応体制の構築
- 法改正のチェックと対応



取得したら終わりじゃないよ!お酒を扱うにはずっと責任がついてまわるからね〜
第9章:ECサイト構築のポイント
- 酒類販売にはフォームなどの「年齢確認システム」の実装が必須
- 決済手段や配送方法は信頼性の高いものを
- 商品ページには原材料・アルコール度数・容量など明記
第10章:まとめ
通信販売酒類小売業免許は、EC市場でお酒を販売したい方にとって非常に有効な免許です。ただし、取得には専門的な知識と準備が必要であり、安易な申請では通らない場合もあります。
副業としてのスタートにも向いていますが、法令遵守や体制整備をしっかり行うことが成功の鍵です。
必要書類の準備や管轄税務署との折衝が不安な方は、専門家への相談も視野に入れて、確実な取得を目指しましょう。



通販免許は、しっかり準備すれば取れる免許!だけど、法律もルールもあるから、そこはちゃんと守って、楽しい酒販ビジネスを始めようね〜♪